ここから本文です。
めぐろ区報令和7年6月15日号編集後記「めぐろ外来生物ノート」
特集「めぐろ外来生物ノート」
気づいてほしい 人間が拡めてしまっていること。
今回の特集は、外来生物。もともと住んでいなかった場所に定住したいきもので、日本では約2,000種の外来種が確認されているそうです。その中でも、生物多様性など環境を脅かす存在として認識され、これ以上拡散しないよう気をつけるべき4種のいきものを紙面で紹介しています。
でも、決して外来生物が極悪非道のいきものではないことも知ってください。これらは日本を侵略しようと企んでやってきたわけではなく、人間の都合で連れて来られ、人間の勝手で捨てられるなどして拡散していったいきものたち。ただ、島国で穏やかに暮らしてきた日本の在来種に比べて、大陸育ちの外来種の多くはとってもたくましい。だから、日本中で幅を利かせることになってしまったというわけです。
その名の通り、アメリカからやってきてついに全国制覇!
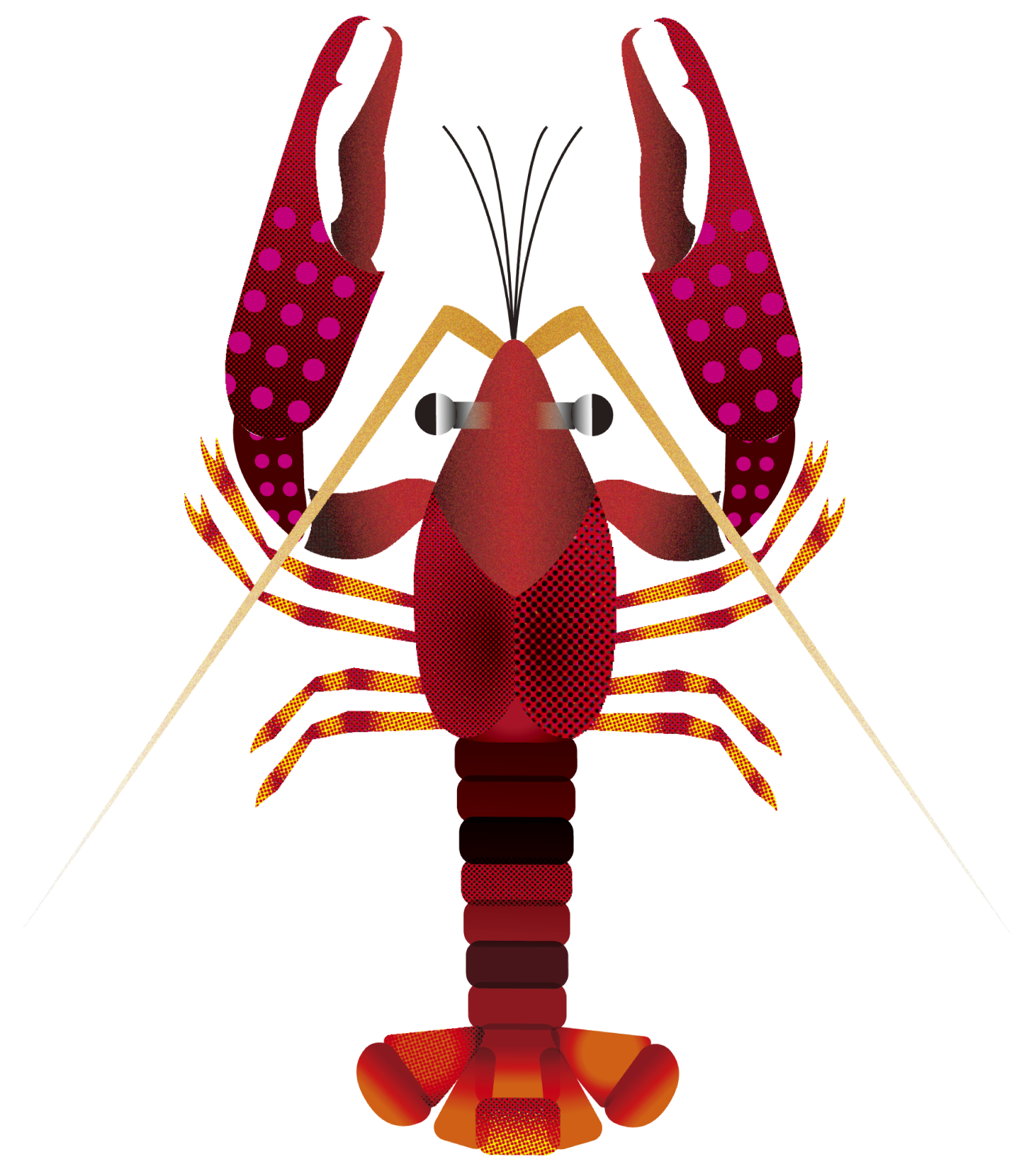 その一例が、紙面にも登場しているアメリカザリガニ。
その一例が、紙面にも登場しているアメリカザリガニ。
昭和2年ごろ、食用とするために輸入したウシガエル(これも特定外来生物)の餌として、はるばる太平洋を越えて輸入されてきました。最初に入ってきた数は、なんと20匹程度だったとか。それが、養殖所から逃げ出すなどして各地で繁殖し、今では北海道から沖縄まで生息が確認されているという、すごい生命力の持ち主です。1匹で数百個の卵を産むというから、まさに最強ですね。
大好きだったから知った「アメリカザリガニって意外とワルモノっぽい」
特集内でお話をうかがった東京大学の公認サークル「環境三四郎」の中野和真さんは、その活動として、東大駒場キャンパス内の駒場池(通称「一二郎池」)に繁殖しているアメリカザリガニの調査をされています。
中野さんいわく、「池の水草をぶった切るから他のいきものは住めなくなるし、水中生物から落ち葉まで何でも食べて、どんどん増えて、駒場池はほぼアメリカザリガニです!」。

取材中、中野さんが見せてくれた駒場池の網にかかっていたアメリカザリガニ。
「大きいハサミだけじゃなくて、他の脚もハサミになっているんですよ」
そんな中野さん、子どもの頃は「アメリカザリガニはカッコイイから大好き」だったとか。好きだからこそ、もっと知りたいとアメリカザリガニを調べるうちに、環境には困った存在であることを知ったそう。
中野さんに区民の皆さんへ伝えたいことを伺うと、「草花や昆虫など、私たちの身近なところに、たくさんの多種多様な外来生物が生息して、どのいきものもみんな懸命に生きています。豊かな自然を守っていくために大切なことは、何が良いとか悪いとかではなく、私たちがさまざまないきものにも関心を持つことだと思います。ぜひ野外に出て、観察に挑戦してほしいです」と話してくださいました。

中野さんの学業は海洋プランクトンの研究だそうです(東大駒場池の前で)
いきもの観察が楽しくなる!中野さんおすすめのアプリ・ウェブサイト
「いきものの種判別に自信がないかたでも気軽に使えます。こうしたサービスを使って、観察を楽しんでもらえたらうれしいです」と中野さん。
|
いきものコレクションアプリ Biome(バイオーム) |
|
iNaturalist(アイナチュラリスト) |
環境三四郎の駒場池ツアー
環境三四郎では活動の一環(池プロジェクト)として、東大駒場キャンパスに生息するいきものを解説する駒場池ツアーを、年に数回開催しています。環境三四郎のウェブサイトで、開催時に募集しているので、興味のあるかたはぜひチェックしてご参加ください。
私たちにできること、それはいきものや自然に関心をもつこと
法律で取り扱いが規制されている特定外来生物ですが、アメリカザリガニとミシシッピアカミミガメだけは条件付特定外来生物として、捕獲して家で飼育することが許されています。やってはいけないことは、もう飼えないから、かわいそうだからと逃がしてしまうこと。
駒場野公園の大池では、池の水を全部抜いて「かいぼり」を行い、アメリカザリガニを取り除いたにも関わらず、その後もアメリカザリガニは確認されています。池底の土に潜っていたものもいれば、水源からやってくるものもいるとか。つまり、一度拡がってしまうと、それを抑えるのは不可能に近いということ。
私たち人間はこうしたことを知り、意識していきものに関心を持つこと。これが、かけがえのない自然環境を守ることにつながっていくんだと思います。
外来生物について、漫画や動画で面白く見ることができる環境省のウェブサイトがあります。こちらもおすすめです。
ヤナミ
こちらの記事も読まれています